【総括】2025年7月21日~8月21日
僕にとってこの1か月は「写真記憶(写真凍結)」の基礎を固めるための、まさに“集中月間”でした。
テーマはずばり――サムネ法の徹底強化。
これまで試してきた色々な方法の中で、いちばん効果を感じたのがこの「サムネ法」だったからです。
■ サムネ法に集中した7月のトレーニング
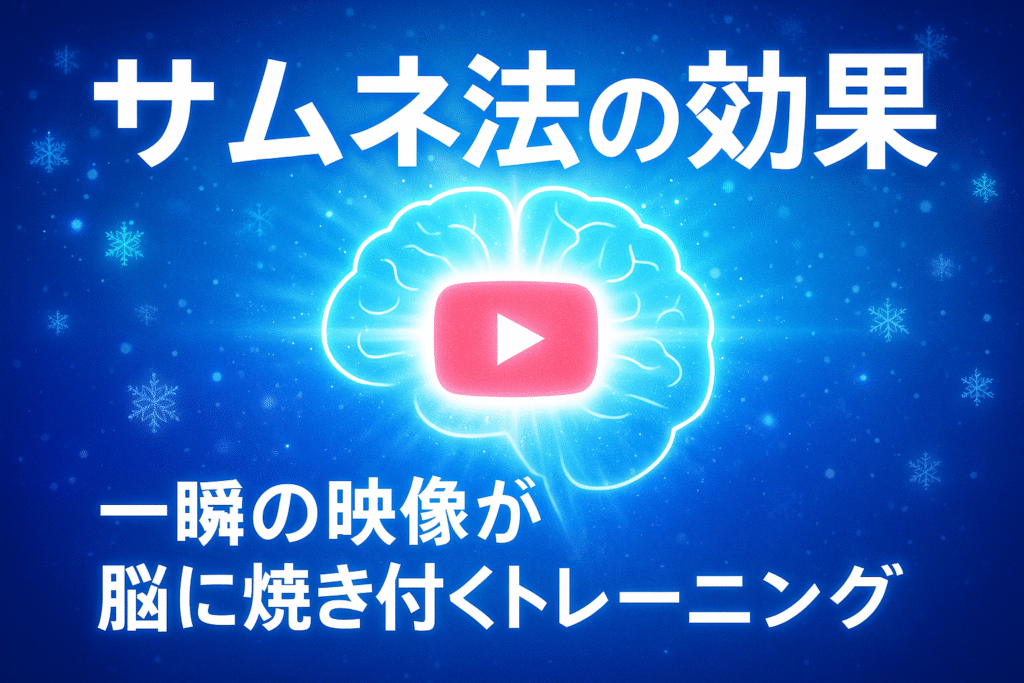
一か月はほとんどの時間を、YouTubeのサムネイルを使った記憶訓練に費やしました。
1枚の画像を一瞬で捉え、暗転後にできる限り正確に思い出す――
このシンプルな繰り返しを、毎日コツコツ続けていました。
途中からはiPadを使うようになり、**3枚のサムネを同時に表示する「三枚法」**にも挑戦。
これにより、一度に複数の情報を処理する能力や、視野の広さを意識的に鍛えられるようになりました。
最初のうちは、1枚だけで頭がいっぱいでした。
でも、続けるうちに3枚の構図全体をぼんやりとイメージで捉えられる瞬間が増え、「あ、見えてる」と感じられるようになったんです。
■ 良かった点:とにかく“時間”をかけたこと
この月のいちばんの成果は、「時間を惜しまず費やしたこと」に尽きます。
特に休日には、1日3時間ほどの特訓を実施。
30分トレーニング → 30分休憩 → 再開、というリズムで続けていました。
最初の15分ほどで脳が温まり、残像が安定してきて、
“見えていく感覚”が徐々に掴めるようになる。
この手応えを感じた瞬間が、何よりモチベーションになりました。
加えてiPadの大画面を使うことで視覚情報の解像度が上がり、
「細部を覚える力」も少しずつ伸びていった気がします。
最初は形だけを追っていたのが、今では色や構図、文字の配置まで自然と意識に残るようになりました。
■ 悪かった点:休憩の長さと集中の切れ目
一方で良い面ばかりではありません。
やってみて感じた一番の課題は、休憩時間の長さです。
集中して30分トレーニングをした後、気づけばスマホで動画を見たり、
SNSを開いたりして休憩がいつの間にか1時間以上になってしまう…。
そうなると、次の特訓のときにはすっかり集中力が切れてしまっていました。
写真記憶のトレーニングは、筋トレと同じように「リズム」が重要。
休憩を挟みすぎると、せっかくの“集中モード”がリセットされてしまうのです。
さらに、YouTubeのサムネを使っていると、どうしても興味を引く動画が目に入ってしまうのも問題でした。
「あ、これ見たいな」と思ってしまうだけで集中力が一気に乱れ、
“記憶のために見ている”という意識が薄れてしまう瞬間がありました。
■ 慣れによる「作業化」現象

もうひとつ気づいたのが、脳が慣れてしまうことの怖さです。
サムネ法を繰り返しているうちに、最初のような新鮮さが薄れ、
「次はこれ、はい見た、閉じて思い出す」という流れが完全に作業的になっていました。
最初は目の奥で残像を追いかけて、形や色を感じる緊張感がありました。
でも、慣れてくると「考えなくても分かる気がする」という錯覚が生まれる。
実際にテストすると、思い出せていない部分が多く、
“やったつもり”になっていたことに気づかされました。
この経験から、常に負荷を変える必要があると学びました。
1枚 → 3枚、静止画 → 動画の一瞬の切り抜き、など、
脳が「おっ?」と思う刺激を与えるのがポイントだと感じます。 自転車で例えるなら、補助輪を両方付けていたのを片方だけ外すようなイメージです。 (例えが下手ですいません) とにかく脳に負荷を掛けるのが大事だと感じました。
■ 今後への改善と次のステップ
7月を通して、写真記憶のトレーニングは確実に進化しました。
しかし、課題もはっきり見えています。
改善点まとめ
- 休憩時間と訓練時間の見直し
- 見るサムネを“カテゴリごと”に分けて刺激を変える
- サムネ法以外の方法を検討
- AIを使い記録、また訓練内容を考えてもらう。
これらを意識しながら、8月は“正確法”や“残像安定法”など、
さらに上位ステップへ進みます。
■ まとめ:「脳を鍛える基礎体力作り」の1か月だった
振り返れば、7月~8月はとにかく脳を使いまくった月でした。
1日3時間の特訓を続けたことで、頭の奥が筋肉痛のようになる感覚もあり、
「確かに脳も筋肉と同じように鍛えられる」と実感。
そして何より、「続ければ必ず見える世界が変わる」という感覚を掴めたこと。
これがいちばんの収穫でした。
📘 今回の学び
・集中時間の質を上げることが一番大事
・慣れは成長の敵、刺激を変え続けること
・量をこなすほど、脳の反応が速くなる
次の1か月は、サムネ法で得た基礎をもとに、
「正確さ」と「スピード」を両立させるステージへ――。
9月もまた、挑戦が始まります。 思い出しながら書いてるので一部あやふやですがご了承ください(笑)
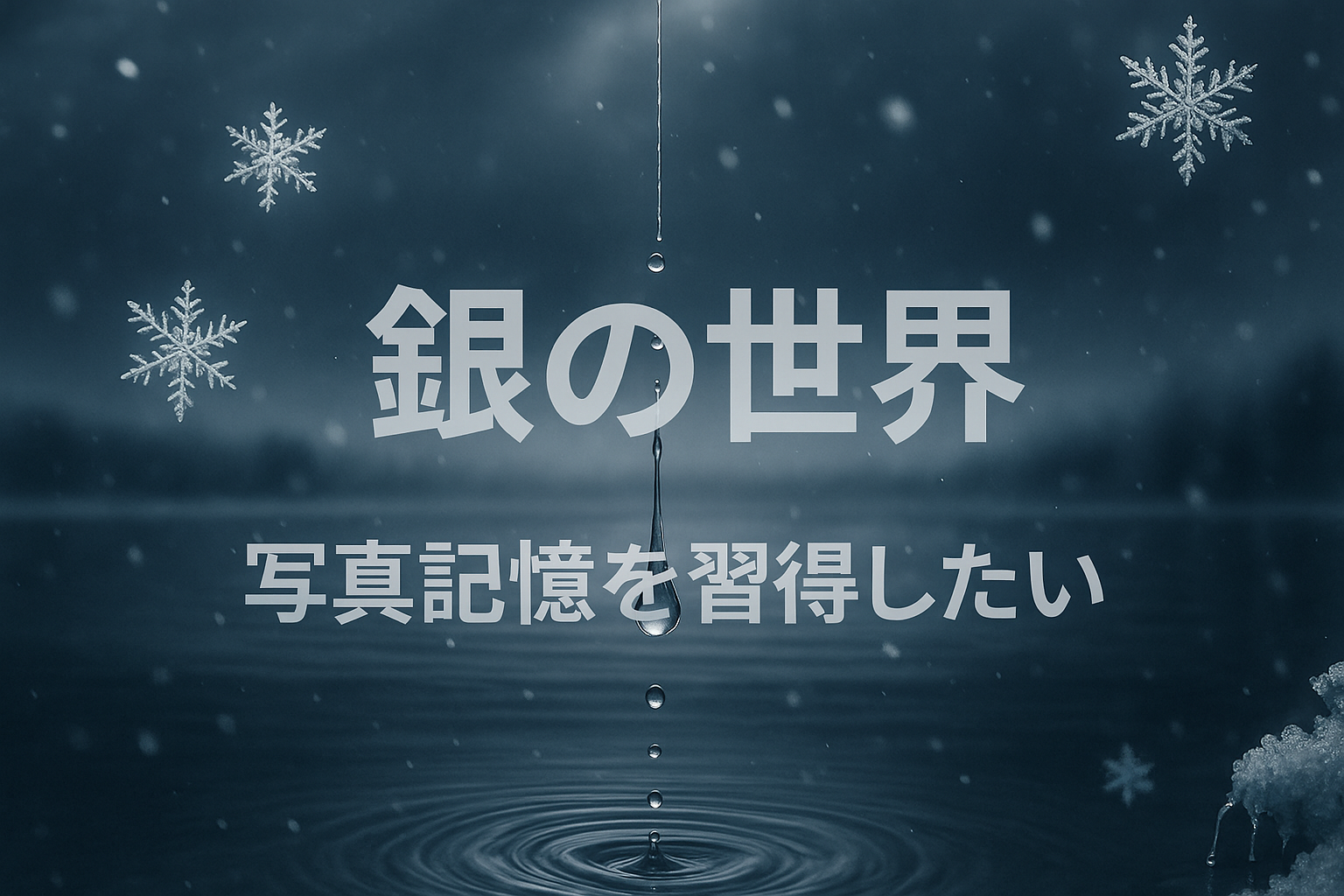
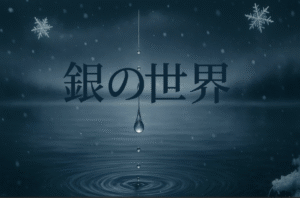

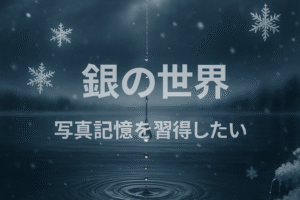
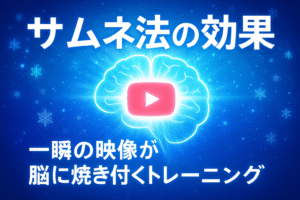
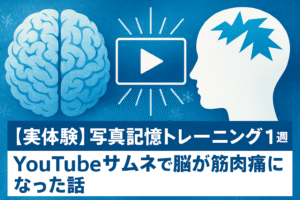
コメント